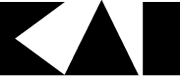
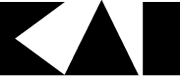
プロの料理人をはじめ料理家の先生方監修のオリジナルレシピや
貝印製品を利用したおすすめレシピなどをご紹介します。
鯛の頭や骨からとった出汁で炊き上げるリゾットは風味良く、贅沢な味わいです。九条ネギをたっぷりと添え、やさしい味わいに仕上げました。
(6人分)
| 鯛 | 1尾(1キロ前後のものを使用) |
|---|---|
| 長ねぎ(スープ用) | 20g(青い部分でもよい) |
| 長ねぎ(リゾット用) | 40g(白い部分) |
| セロリ | 20g |
| 白ワイン | 50cc |
| 無塩バター | 20g・40g・20g |
| 水 | 1500cc |
| 米 | 2合 |
| 九条ねぎ | 12cm |
| プチトマト | 12個 |
| 塩 | 適宜 |
| こしょう | 適宜 |
| ローリエ | 1枚 |
 |
出刃包丁で鯛を3枚におろす。骨で出汁(フュメドポワソン)を取るため、頭を真中で割り、えらを外す。骨は2~3か所で切る。骨と頭をザルにのせしばらく流水にさらす。身は1.5㎝幅に切り、塩・こしょうをふる。 |  |
|---|---|---|
 |
セロリは4mm幅の薄切り、長ねぎは1センチ幅に切る(スープ用とリゾット用)、青い部分は大きめに切っておく。プチトマトは半分、九条ねぎは小口切りにする。 | |
 |
鍋に20gのバターを熱し溶かし、1の頭と骨、2のセロリ・スープ用長ねぎを加えて骨の周りの身が白くなりほぐれて魚とバターのよい香りがするまで炒める。白ワインを加えて沸騰させたら水を加え再び強火で沸騰させ、しっかり灰汁を取りローリエを加えて20分煮て濾し、塩・こしょうで味を整えておく。(フュメドポワソン) | |
 |
フライパンを温め、バター40gを入れ鯛を皮目を下にして焼き、9割火が通ったら皮目を上にして取りだす。長ねぎを炒める。長ねぎの甘い香りが出たら米を加え、中火で米が熱くなるまで炒める。熱々に熱した3の1/4量を加え中火で混ぜながら加熱する。水分が減ってきたら3を4回に分けて全て加える。 | |
 |
プチトマトを加え、味見をし、米の固さをみる。アルデンテがよい。塩・こしょうで味を整える。バター20gを加えて全体をよく混ぜたら完成。器に平たく盛り、4で取り出した鯛と九条ねぎの小口切りをたっぷりとのせる。 |
 |
お米はとがずに使用しますが、気になる方はさっと洗ってよく水気を切ってから調理をはじめてください。鯛は焼き過ぎず、皮目だけを焼き、あとは余熱で火を通します。 |
|---|
格別な切れ味と耐久性を備えた逸品・湿式平前刃付け:非常に細かい砥石で刃付けを行うことが可能で、繊細な 切れ味を実現。熱による硬度ドロップも回避できるので、高硬度を維持しながら刃付けを行うことが可能です。・ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。・手にフィットする八角形状の積層強化木柄。・刃体は樹脂との同時成型により、刃と口金部の境目に隙間がなく衛生的。独自の接合方法でより高い耐久性を実現させました。・使用後は速やかに汚れや水分を取り除いて乾燥させ てください。汚れや水分を残したまま放置するとサビや変色の原因になります。
伝統の鍛造製法による 本格ハガネ和包丁・ハガネ複合材:ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた、強靭な刃身。ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現。・水牛製の口金:堅牢で耐久性と耐水性に優れた最高級素材。水を吸うを締まる性質を持っているため刀身が抜けにくい。・湿式平前刃付け:非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら 行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。・手になじむ天然木の柄。 ・サビやすい「ハガネ製」です。使用後は汚れを落とし、水分をよく 拭き取ってください。汚れや水分を残したまま放置するとサビの原因となります。